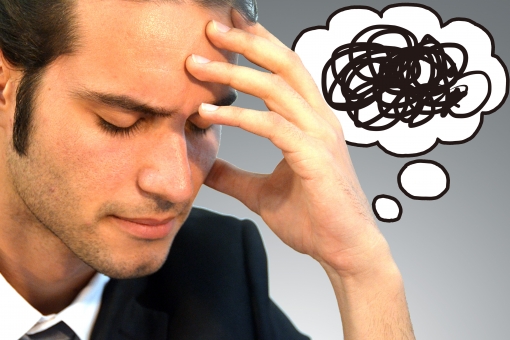人を育てる
せっかく採用した人が育たない。このようなことでは会社は困ってしまいます。育たないどころか皆の足を引っ張ってしまう。こんなことになったら大変です。そうならないように新人(新卒も中途も)が入社したら配属された部門の人は他人ごととは思わずどうしたら最も早いスピードで新人が育ってくれるのか知恵を絞ることが大切です。
■部下を選んではいけない

採用を担当する人と、採用された人と一緒に仕事をする人(採用された人が配属された先の人)は殆どの場合異なります。時々起るのが、採用した人(人事や総務の人)は、この応募者はイイと思って採用したのに、その新人が配属された先の担当者(達)はそう思わないというケースです。部下は上司を選べないが上司は部下を選べると時々言われてきました。でもこれは間違い。上司(先輩)も部下(後輩)を選んではいけません。自分が使いやすい人間のみ周りに揃える、では会社は成長しません。いろいろな個性があってその個性を活かすことを考えます。人生いろいろなところで人との縁が生まれます。会社も同じです。配属されてきた新人を任されたら徹底してその人を育てる方法を考えなければなりません。自分が選んだ人間ではないので自分は知らない、とか、自分は育てる気はない、では社会人先輩としては済まされないことをまず認識する必要があります。本来このような考え方ができる人が組織には揃っていなければいけないのですが、悲しいかな現実はそうではありませんね。こんな現実を捉えて、採用担当者としてどう動けばいいのか探ってみましょう。
■担当者が直接面接
通常面接は、一次・二次・三次と回数を重ねるごとに職責の大きい人が順次担当していくことになります。最終面接が社長面接とか役員面接という企業が多いことと思います。前述の採用された人と現場の考えの食い違いを避ける方法として、面接の段階で担当セクションの担当者に面接担当させてしまうのが一番確実な方法です。大手企業のように十羽ひとからげで採用し研修と同時に配属先を決めていく場合にはこの方法は使えませんが、中小企業の採用であれば、どこかの段階で、配属先担当者と応募者が面談できる日程セッティングは可能ではないですか。この時、配属しようと考えている部門のリーダーに参加してもらうのがいいでしょう。リーダーが直接目で見て会って話すことで応募者が配属された後のチームのカタチをイメージできるのでミスマッチを減らすことができます。またチームメンバーとも入社前に情報を共有することができるのでチーム力強化にもつながっていきます。面接の段階で配属先セクションの担当者面接機会をつくる。ぜひ取り入れていただきたいと思います。
■自分で盗む心持が人を育てる
次に人を育てる時の要諦を考えてみたいと思います。新卒の場合、まず最初に、社会通念や会社文化からビジネスマナーを教えていきます。これらは会社の人間が担当するというより研修期間中に専門講師を通じて教育されることも多いかと推測されます。問題は配属後そのセクションごとの専門職(現場)教育でしょう。この教育は習うより慣れろの言葉どおり先輩や上司について自ら感じさせ習得させることが一番です。ですからまず最初にそのような教育方針を新人に説明し、自分で考え実践し改良することが基本だよと教える必要があります。実はここで勘違いしている人を良く見受けるのですが、それは、習うより慣れろ、自分は何も教えないし言わないので仕事のやり方は自ら盗めと考え、新人に何も指導しない人がいます。勘違いしてはいけないのは、指導教育は必要です。新人の心持を、「自ら盗め」という気持ちに持っていってもらうことが肝心で、そのことと何も指導しないで知らんぷりとは大きく違います。放任と干渉の両輪。そのような気持ちになって必要に応じて適切なアドバイスを行っていける人が教育者指導者として有能な人です。
■根掘り葉掘り教えない
仕事が出来る人が増えれば会社業績は上がります。増えなければ業績は低迷してしまいます。ではどうすれば仕事ができる人を増やすことができるのでしょうか。仕事ができる人は自分の考えを持った人です。自分の考えを基本に人と話し仕事を組み立てていくことができます。ですからまず自ら考えて行動できる人を増やしていくことが近道です。そのためには根ほり葉ほり教えない。よくこんな会話に出くわします。部下が上司のところにやってきて、「どうすればいいですか」と質問する。この時、すぐに答えや指示を与えないこと。「どうしたらいいと思うか」と相手に考える時間を与えます。そしてその回答が返ってきて初めてレビューしてあげます。「ここはいいけどそこはこういう方法がいいよ。なぜならこういう理由で・・・」とアドバイスしてあげます。この繰り返しでだんだん自分で考え行動する習慣が生まれ仕事を切り開いていける人間に成長していきます。「なぜならこういう理由で」。実はこの背景を教えてあげることが大切。もちろんそれを教えず考えさせる訓練も有効です。このことはまた機会を見つけて触れたいと思います。