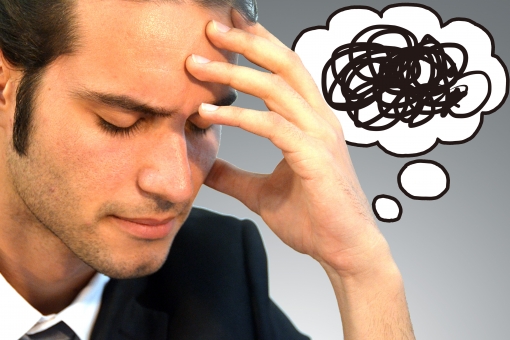経団連、採用選考指針を考える
経団連、採用選考指針とは何でしょう?経団連が加盟企業に対して示す新卒採用活動の原則(自主採用、罰則なし)です。「公平・公正な採用」「正常な学習環境の確保」に加えて「採用選考活動の開始時期」も定めています。これによると2017年卒業予定の大学生・大学院生の採用活動解禁は、大手就職ナビや説明会などの広報活動解禁が3月1日以降可能、面接・採用試験などの採用選考活動が6月1日以降可能となっています。これが、よく巷で言われている採用選考指針(自主協定)です。
■ここ数年、毎年のように変わる広報活動解禁と選考活動解禁

2015年卒業者は2014年12月1日/4月1日。2016年卒業者は2015年3月1日/8月1日。2017年卒業者は2016年3月1日/6月1日。何の日付かというと、それぞれの卒業年度に卒業を迎える学生に対する採用活動(広報活動解禁と選考活動解禁)のそれぞれの日にちです。学業優先を目的に、あるいは就職活動の長期化を防ぐことを目的に制定されていますが、ここ数年では毎年ネコの目のように内容がコロコロ変わる協定となっています。
■経団連加盟企業と非加盟企業
加盟企業は大企業、非加盟企業は中小企業という分け方が一般的です。加盟の大企業も非加盟の中小企業も採用ということで考えると、人財は企業の明日を支えていく逸材なので、みんな喉から手を出したいほどいい人財を採用したがっています。それが企業の10年後、20年後、30年後を決めることになるからです。今、企業で役職について需要な仕事を切り盛りしている人も30年前に戻ればその時はただの大学卒業者でした。資本主義の競争社会では、競合他社に先駆け抜きんでていくために、優秀な人材の獲得が必須と言えます。若い人が企業を活性化させ企業の未来を創っていきます。そういった企業活力となる若手(学生)を一時に大量に採用できる絶好の機会が新卒採用です。中途で優秀な人はなかなか大量には採用できません。こう考えていくと、大企業も中小企業も新卒採用に躍起になるのも大変よくわかるし、その結果、報道のように、協定やぶりが横行しても、無下に責められないともいえるのではないかと思えます。
■就活(採活)スケジュール、ルーチン化が一番
そもそも何のための採用指針なのでしょうか。学生の学生としての期間を尊重するため、学業を優先させるため、と言われています。それでは、何のためにみんな大学で学んでいるかと考えると、それは、将来自分が考えているライフワーク(仕事をふくむ)を有意義に行うため。その準備段階として学生時代があるとも言えるのではないでしょうか。自分が興味のあることを勉強し、それを社会で活かすために学業に励んでいる。こう考えると就職活動もそれぞれの人生を生き抜くための学業のひとつとも捉えることができます。そもそも優秀な学生はそう多くの時間を使わなくても目当ての企業に就職できるし複数の内定をもらうことになると思います。ですから就職活動で多くの時間をとられるというのは就職活動中の学生全般に当てはまることではないのです。就職が早く決まる人は採用指針がどうであれ、早くに決まるし、そうではない人は長い時間と多くの回数を就活に費やすことが必要になってきます。こう考えると就職協定は毎年固定(ルーチン化)して企業側にも安定した(毎年同じスケジュールで活動してもらう)スケジュール感をもってもらい、学生も先輩の活動を参考に(先輩の講堂スケジュール通りに)余裕を持って就職活動できる環境を持ってもらうことが一番な気がします。
■就活はじっくり腰を据えて行うべき
就職活動は人生で一度はみんな経験する一大事業です。一生を左右するような大事な活動です。ですから、学生は就活に時間をかけるべきだし、その時間を惜しんではいけないと思います。この際に大事なことは無駄な就活はするべきではないということではないでしょうか。無駄とは、本来望んでいない業界には行かない。行っても徒労に終わる説明会や面接には行かない。徒労に終わるとは、企業側で暗に指定校を設定していてそれ以外の学校の学生は行ってもはじかれてしまうような会社を選んでしまった場合などです。○○大学(例えば偏差値○○以上の大学)以外の学生以外は採用しませんと公式発表してくれていれば別ですが一般的にはそのような情報は公に発表されていないのが常です。しかし実際にはそのような選定は確かに存在しています。業界や仕事をよく研究してその業界の先輩に会って話を聞いてじっくり就職先を探す。こんな就活をしてほしいと思います。