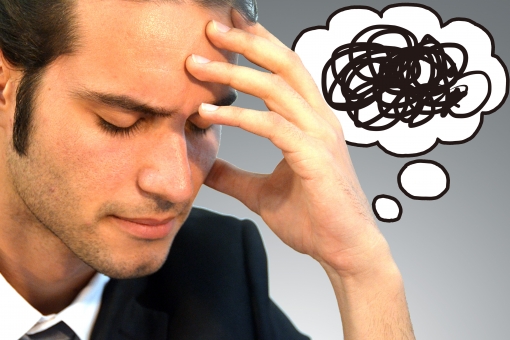留学生にもインターン
2016年9月14日付け日本経済新聞朝刊に、留学生対象のインターンに関する記事が掲出されていました。
今後、若年労働力の減少が確実な現状で、留学生インターンによる外国人労働力の確保も、今後の人財活用のひとつとして検討できるのではないでしょうか。
■外国人留学生向けにインターンシップ

(以下記事より抜粋)
「ONSEN」という表記では、外国人に伝わりにくいですね」京都市内にオフィスを構える出版社のリーフ・パブリケーションズ。9月2日、京都大学に通う中国人留学生の範欣旅さん(24)は、訪日外国人向けのフリーマガジンを手に編集者と真剣な顔で意見を交わしていた。範さんは同社で約2ヵ月のインターンを予定しており、この日が初出勤。京大では修士課程で経済学を専攻する。出版社の職場は、「慣れないことばかりだが仕事の内容が新鮮」と目を輝かせる。将来は日本で働くことを希望しており、インターンは「今後の就職先選びにとても役立つ」(範さん)と話す。
一方のリーフ社は主に地元住民向けのタウン誌を作っており、現在は外国人の社員がいない。ただ最近は訪日外国人を対象にした仕事が増えているため「留学生のインターンを受け入れ外国人社員を確保したい」と編集長の上山賢司氏は語る。
範さんのインターンを仲介したのは京都府内の約50大学が加盟する公益財団法人大学コンソーシアム京都(京都市)だ。2015年5月に留学生の就職支援などを手がける組織「留学生スタディ京都ネットワーク」を地元経済界などと立ち上げ、16年度から留学生向けインターンを始めた。今年9月から、外国人採用を検討している地元企業15社がインターンを実施。業種は出版のほか、仏具や菓子メーカーなど多彩だ。参加する22人の留学生の出身国も中国やマレーシア、フランスなど様々。いずれも80時間の就業体験を予定し、留学生はその間の給与と交通費を得られる。「留学生の受け入れから就職までの送り出しを地域一丸となって支援したい」。同財団の蔵重暢宏主幹はこう語る。京都市は人口に占める留学生の比率が全国トップだが、地元の中小企業に就職する留学生はまだ少数という。インターンを通じて、学内にいただけでは知り得ない「日本企業の現場を知って就活に役立ててほしい」(蔵重主幹)との思いがある。
マレーシアからの留学生、ヌル・アミナ・ビンティ・モハメド・カイリさん(22)もインターンに参加した一人。普段は立命館大学で機械工学を学ぶが、プレス加工の山岡製作所(京都市城陽市)で製造ラインの組み立て作業を体験した。「講義では経験できないものづくりの現場を知ることができた」と喜ぶ。(以上抜粋)
■将来に備えて外国人を採用
ビジネスの垣根がなくなって国際間の人事交流がさかんになっている今、国際感覚豊かな留学生(外国人労働者)の採用を行う企業が増えています。
たとえば、中国に製造拠点を設ける場合、勝手がわからない日本人が担当するよりも中国人を採用してその方法を模索したほうがはるかに効率的だしビジネス上でも何かと有利に働くでしょう。今後、中国にかぎらず、フィリピンなどの東南アジア諸国や中東、南米など、経済発展が展望できる国では、この動きは顕著になるはず。その時にあわてて採用するよりも今の内から準備しておこうという企業が増えている背景は大いにうなづけます。
留学生インターンから社員採用となれば、日本人とは違った研修過程も必要となるだろうし、就労許可の手続きも必要となるでしょうから、超えなくてはならないハードルもあると思います。そのあたりを押してでも、今、留学生就職マーケットは熱さを増している様子です。