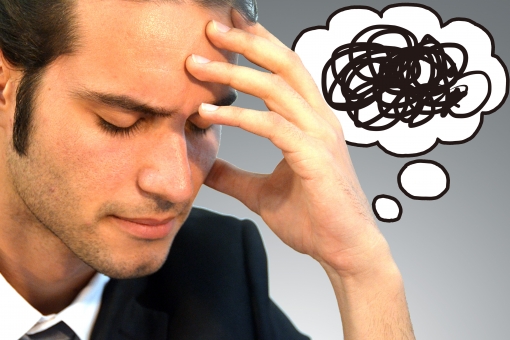有効求人倍率上がっても・・・
5月31日厚生労働省発表、有効求人倍率は1.34倍。
有効求人倍率とは、仕事を探す人一人に対して何件の求人があるのかを示す指標です。1.34倍ということは、仕事を探す人ひとりに対し、1.34件の求人企業があるということになります。
求人する企業が仕事を求める人よりも多い、ということは、景気判断のひとつの指標として捉えると、景気が良くって、企業がやるべき作業(生産)が多いので、それを賄うために、労働力を欲している企業が多い環境下にあるということになります。
つまり景気がイイ、はずなのですが・・・。しかし、いまひとつ景気感に波及していない。これはいったいどうして?
■働いてみたい仕事が少ない。

[2016年6月1日日経新聞朝刊より]
求人はあるけどやりたい仕事じゃない。2013年11月に1倍を超えて以降、企業が求人を出しても条件が合わずに思うように採用ができない状況が続いている。有効求人倍率の割に景気がさえなく見える要因の一つがこんな「雇用のミスマッチ」で、企業業績の足かせになりつつある。(中略)非製造業では慢性的な人手不足が解消できないため、求人倍率が押し上げられている。厚労省は「人手不足が深刻な一部の業種で、求人を繰り返している」と分析する。ゼンショ―ホールディングスの牛丼店「すき家」は4月末時点でも228店で深夜営業を休止中だ。人出不足を理由に14年10月に約1200店の深夜営業を休止した。アルバイト確保を進め、営業再開店舗を増やしてきたが「全店再開のめどはまだ立っていない」(同社)という。
求人する企業の思惑と職を求める人の希望、両者のベクトルが合っていないと、前述のような事態に陥ってしまいます。とくに労働集約型のビジネスを展開する企業では、働く人手があってのビジネスなので、その人手が確保できないとお店をや工場を閉めざるを得なくなります。そうなると生産性も落ちるので売上利益も落ちます。売上利益が落ちるとそこで働く労働者の所得も落ちるので景気が悪くなります。負のスパイラルに落ちいってしまいます。
■女性や高齢者が中心の求人
[2016年6月1日日経新聞朝刊より]
雇用が増えているのが、高齢者や女性の非正規労働が中心であることも、求人倍率の伸びの割に景気が盛り上がらない理由だ。食品スーパー最大手のライフコーポレーションは16年3月から順次、70歳を超えてもパートを継続雇用できるようにしている。首都圏地盤のマルエツでも15年度から、70歳以上の人でもレジ打ちや鮮魚加工で働けるようにした。(中略)正社員が増えるなど雇用情勢がもう一段良くならないと、消費改善にはつながらない。(後略)
企業にとって、現代は大変難しい経営を強いられる時代と言えます。少量多品種時代、飽食時代、ネット情報時代。大量に楽に売れる時代はとうの昔に過ぎ去って今ヒット商品を出すことが難しくなった時代です。仮にヒットしてもすぐに飽きられて長続きしてくれません。ですから、長期で雇用を保障しなければならない正社員は雇いづらい時代なのです。今後企業は高齢者や女性を効率よくうまく雇用する必要に迫られます。高齢者も女性もどんどん働いてもらい国内の生産力を上げていく必要があります。そんな皆さんが増えれば、購買力も上がって景気回復にも大きく貢献するはずです。
■生産年齢人口が減っている

[2016年6月1日日経新聞朝刊より]
就業地別の求人倍率でみると、05年2月に集計を開始して以来、初めて全ての都道府県で1倍を上回った。求人倍率が低い都道府県をみると、沖縄を除くと、高知県、鹿児島県、北海道、青森県などで、「少子化で求職者数が減っている」(厚労省)。若者が都会に出て、就職するケースも多いとみられ、地方の求人倍率の改善につながっているようだ。(後略)
少子高齢化ということは若い人が少なくなって高齢者が増える現象にあります。これは、ここ十数年の現代日本の傾向なので、周りがどうあがいても変えようがありません。少子なので子供が少ない。子供が少ないので生産年齢人口が減るのも当たり前のこと。何も今に始まったことではありません。この解決策も実は高齢者や結婚退職し子育て中の女性の活用にあります。高齢者を積極的に採用しその人生キャリアを活かしてもらうことです。子育て中の女性でも短時間勤務できるような制度を創って活躍してもらうことです。日本国民総生産を実現し、物づくり日本を復権再生することではなでしょうか。