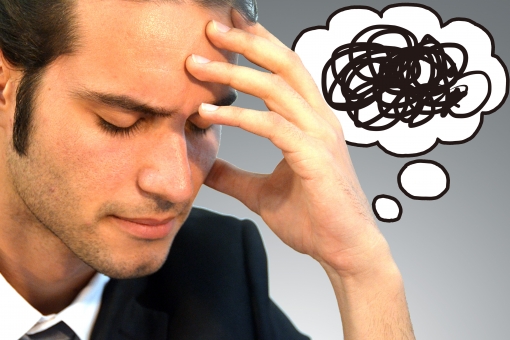学生のこころをつかむプレゼンテーションって?
会社説明会でどんなスライドを使ってプレゼンテーションすれば、学生の心に残って貴社に入社してみたいと思ってもらえるのでしょうか。

説明会実施の際、会社案内、入社案内、概要書、など一式を学生に渡すことが多いと思います。会場にはスクール形式に並んだテーブルとイス、その上に置かれた会社案内や印刷物、だいたいこんなイメージなのではないでしょうか。また説明する人がスクリーンを使ってスライドを操作しながら学生に会社内容や概要を説明する。そのスライド説明のための出力資料(ハンドアウト)もテーブルの上に置いてある。こんなイメージかとも思います。
本来説明に要する資料は少ない方がいいのですが、伝えたいことがひとつの資料に全て 満たされているわけではないのでついついあれもこれも使ってしまいがちです。 では、そんな状況の中、聞きやすくて学生に効果的なプレゼンテーションのためには何をどうすればいいのでしょうか。
まずは、どのツールで何を説明するのかを事前に決めて、一度や二度は実際の説明会と同じ時間を使ってシュミレーションしておくことが基本です。つまり練習ということになります。意外ですが皆さんこの練習をしていません。いきあたりばったりという人が大変多いのです。 これをお読みになっている貴方はいかがでしょう。声に出して一度は練習していますか。セミナースピーチや結婚式スピーチも何でもそうなのですが本番と同じように練習すればスムースにできるし、練習していなければそれなりの結果に終わってしまいます。
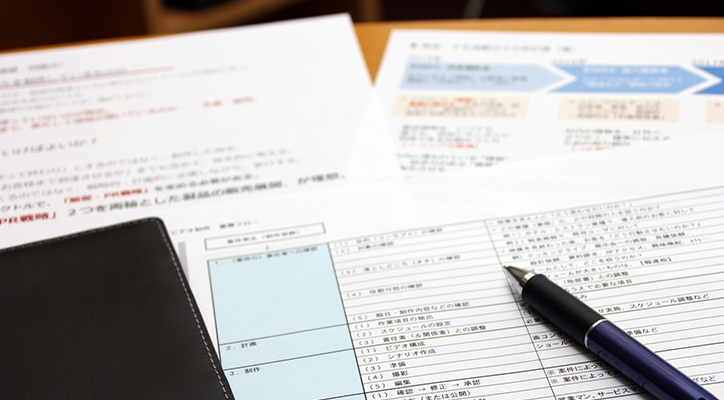
ツール構成ですが会社案内・入社案内を使って会社概要入社案内部分をさらりと説明した後、今が旬な会社情報などはあなたがつくったオリジナルスライドで説明すればどうでしょう。会社案内や入社案内はできれば説明会開始前の待ち時間中に学生にみてもらった方が良い場合もあります。そしてオリジナルスライドによる説明会が始まったらオリジナルスライド用の前方のスクリーン(オリジナルスライド)に集中してもらいます。
オリジナルスライドをつくる場合の要点として、まず全体のストーリーを決めます。このスライドで自分は学生に何をプレゼンしたいのかを明確に整理します。全体のストーリーを決めたらストーリーを構成するパーツをつくります。同時にプレゼンの時間も決めます。目安は1スライド2分~3分といったところです。
そしてここが一番大事な点ですが、スライドはできるだけ見せて説明できるような内容(文字を読んで理解するのではなくスライドを見て理解できる内容)とすることです。文字を極力少なく作成することです。
グラフを使う場合でもその文字要素は減らすことを考えます。どうしても文字で説明したいところはプレゼン資料から一旦はずしてその部分だけ手元資料として印刷して学生に渡してください。
私が日頃思っていること。それは会社説明会の資料に限らず、その他のプレゼン資料も皆さんがつくるものは文字量が大変多いということ。文字量の多い資料は、まずそこに書かれている文字は見えないし読めません。またその内容を説明されても即座にはわかりません。まして記載されている文字要素を全て説明する時間など話し手側にもないのです。つまり本来必要とされない文字が資料の中にたくさん入ってしまっているということになりますね。これでは大いに聞き手にストレスが溜まってしまいます。結果は、聞き手は聞きたくなくなってしまいます。
文字は極力少ない方がいい。これがスライドづくりのデザイン上のポイントです。