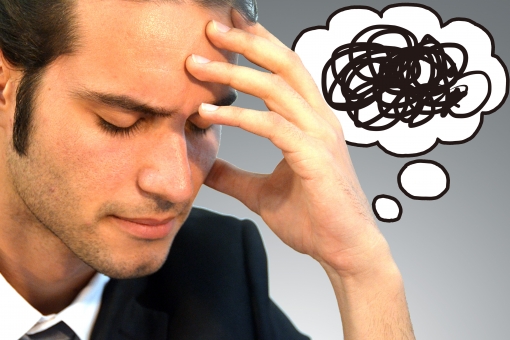始まりは大正時代から!?就職活動の変遷まとめ
就職活動の後ろ倒しなど、スケジュールの変動が何かと多い昨今。今後もスケジュールの変動に眼が離せませんね。ところで、就職活動は一体いつから始まったものなのでしょうか?
今回は就職活動の変遷の歴史について触れていきたいと思います。
■就活の始まり

いわゆる就職活動、選考が始まったのは大正時代まで遡ります。
1928年、今まで大学というと「旧帝大」しかなかった日本ですが、大学を増やして優秀な人材を多く育てていこうと、「大学令」が交付されました。そして関東大震災などの影響で日本は不況に陥り、職を求める学生が殺到。社会はいわゆる「買い手市場」となりました。
そんな中で各社が多くの学生の中から優秀な人材を選び出すための選考が行われるようになります。これが、就職活動のはじまりです。
しかし、選考が始まったと言っても、企業への応募は学校推薦で行われていました。現在のような自由応募の形になったのは1968年以降からでした。
■内定者には海外旅行が!?バブル時代

時代は少し飛んで1986年、空前の「売り手市場」の時代となりました。バブル時代の到来です。
民間企業も好景気により売上が増加、そこからさらなる事業の拡大を図るために多くの募集をかけていました。当時の有効求人倍率は1.4倍と殆どの学生が自分の思い通りの企業に入社できたなんて噂も耳にします。
1991年6月に公開された、『就活戦線異常なし』(フジテレビ・東宝)は当時の就職活動の状況をリアルに描いています。
学生たちが色柄のある派手なスーツを着ていたり、内定者には海外旅行や車、マンションまでプレゼントしてしまう企業もあったり…と今では全くもって想像できない時代でした。
また、この景気の良い雰囲気から広告出稿量の多い大企業や広告、マスコミや外資などの華やかなイメージの企業が学生からの人気を集めていました。
■景気の良さはどこへ…就職氷河期

バブルが崩壊して待っていたのは金融危機やリーマン・ショックなどの景気後退でした。
それに伴ってやってきたのが就職氷河期の時代です。一般的には1993年~2005年前後卒の学生が就職氷河期世代と呼ばれています。
当時、求人数は大幅に削減され、業績復興のための即戦力が求められるようになりました。そのため、自分の希望や適性否応無しに入社せざる負えないため、短期間で解雇されてしまうケースもあったとか。
また、学校側と企業側で就職活動の期間を定めた就職協定も1996年に廃止され、就職活動が早期化および長期化するようになります。
就職氷河期の世代以降から就職においての価値観が変化し、学生は安定性を求めるようになりさらなる大企業志向となっていきました。それにより、中小企業の採用活動がなかなか芳しくなくなっているという課題が生じています。
■スケジュールの変動が激しい現在

そして2016年、政府からの「学生は学業を優先するべきだ」という要請から、経団連は就職活動の解禁を12月から3月に大幅に後ろ倒し、スケジュールは劇的に変わりました。
このスケジュール変動から企業、学生共に混乱。内々定を出した学生に蹴られないために「就活終われハラスメント」、いわゆる「オワハラ」を学生に強いる企業も目立つようになりました。
また、スケジュールを後ろ倒しにすることで2016年度の就職活動は短期決戦となり、早くから準備していた学生とそうでない学生の格差が顕著に現れたとされています。
2016年度の就職活動の状況から、今年度は選考を2ヶ月前倒しになり、さらなる短期決戦となっています。
■まとめ

就職活動の変遷を見てみると、景気の動きに伴っていくことがよくわかります。
昨今では、学生の学業を優先させるためと就職活動の短期化が勧められておりますが、スケジュールを後ろ倒しによってさらなる長期化になってしまっている。という現状が現在の課題です。
それを踏まえて、就職活動のスケジュールは今後も変動していくかもしれません。
企業側も、周囲や環境に惑わされず、企業のビジョンをしっかりと持って採用活動に励みましょう。