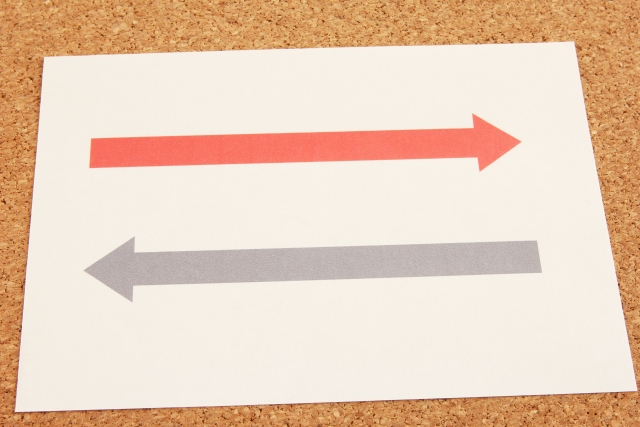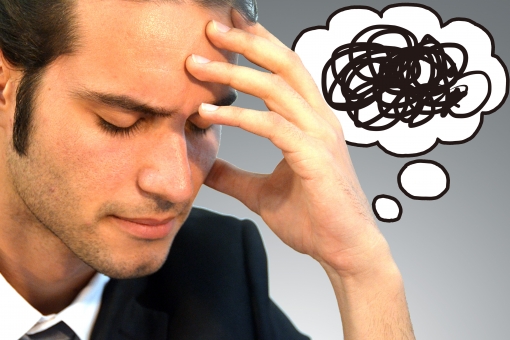内定を巡っての学生意識って・・・
新卒採用では6月が採用活動解禁でした。7月頃の報道ではほぼ半数の学生が何らかのカタチで企業から内定をもらっていると伝えられましたが、内定をもらってから入社を決めるまでの学生の心持や内定後の活動はどうなっているのでしょうか。そのあたりの事情を見ていきたいと思います。
■内定と学生の関係

大手就職ナビマイナビの2016年卒業者対象のアンケー結果から推察していきたいと思います。
まずは第一の質問から。この会社に入社しようと決めた一番のタイミングとして。
一番は「内定を伝えられた時」。二番目が「面接官とのやりとり」。三番目が「人事以外の社員と話している時」。と回答しています。上位三番は全て人がらみのタイミングです。学生がこの会社に入社しようと思う要因にその会社の人間が影響を及ぼすことが見て取れます。
次に内定後入社を決めた企業と接触をもったかどうか。「持った」91%。「持たなかった」9%。で圧倒的多数で内定後接触を持っています。その接触頻度ですが、「1ヵ月に一回程度」が40%。「2ヵ月に一回程度」が28%。このふたつで全体の70%を占めているので、大半の企業が1ヵ月から2ヵ月スパンで内定を出したあと学生と会っている現状が見えてきます。しかし「殆ど接触していない」が全体の約17%存在しているので、企業側は両極端な行動をとっているようです。
次に企業側との接触内容を見ていきましょう。圧倒的に多いのが「内定者同志の懇親会」です。次が「提出書類の案内や事務連絡」です。
次は意外ですが「内定者専用WEBサイト」での連絡。これは専用WEBサイトを構築している企業があるということですがちょっと意外に感じました。WEBを使った連絡のやり取りの方が楽ということでしょうか。また急ぎの用でないことはWEBでやり取りするということでしょうか。時代をみる感があります。続いて「先輩社員との懇親会」と「人事担当者との懇親会」が続きます。
やはり会社側の人間と接触を持ってもらうことで学生をつなぎとめることへの安心感を感じるのだと思います。
■内定式とフォロー研修
内定式に関して見ていきたいと思います。
内定式に参加したことのある学生は70%強。参加したことがない学生は30%弱。この数字から大半の企業が内定式を行っている現実が見て取れます。大企業中心のことかもしれませんが。
では内定式の実施日はいつ?といえばこれは圧倒的多数で10月1日です。9割弱の企業が10月1日を選んで行っています。どうして10月1日なのでしょうか。これは企業側が内定を出せるのは10月1日であると「大学卒業予定者・大学院修了予定者等の採用選考に関する企業の倫理憲章」で決まっているから。つまり今は全社がフライングしていることになるのですね。ですから企業側も10月1日以前は、内定とは言わずに内々定と呼んでいます。
次に内定式に出席するための交通費の負担ですが約8割強の会社が交通費を負担しているようです。せっかく内定を受領してくれた学生に対して非礼のないようにという配慮でしょうか。内定式参加後の企業イメージですが、参加する前より良くなったという学生が約3割、あまり変わらないという学生が6割強。けっして学生のイメージアップにつながっているとは言えない結果ですが内定式はひとつのけじめであると考えるとやはり必要なのでしょう。
興味深いのは、内定者フォローアップ研修を受けたいか受けたくないかという質問に関しては約8割の学生が参加(受けたい)を希望していること。やはり少しでも企業の雰囲気や仕事に触れていきたいという学生心情が反映されているのでしょう。アンケートでも、「入社後の仕事について深く知りたい」、「内定者同士の人間関係を深めたい」、「職場の雰囲気を知りたい」、「社会人としてのスキルマナーを身につけたい」、という回答が多く寄せられています。フォローアップ研修の頻度は1ヵ月に一度が45%、2ヵ月に一度が38%と殆どの企業が1ヵ月~2ヵ月に一度の研修を行っているようです。
学生が希望する研修内容は「、内定者懇親会」、「先輩社員との懇親会」、「勉強会・グループワーク・研修会が上位3位となっています。人との繋がりを持ちたがっていることが見て取れます。受けたい集合研修の内容は、「ビジネスマナー」67.7%、「仕事理解・会社理解」62.8%、「コミュニケーションスキル」が40%、「社会人意識醸成」が35.8%、「仲間意識醸成」が27.8%、「ロジカルシンキング」が26.9%、「思考力強化」が25.8%、「キャリアデザイン」が22.8%となっています。(複数回答)。「仕事理解・会社理解」はその会社独自のものですから実際に会社に触れないと勉強できませんが、その他の希望項目はそれらに関する書籍も多数出版されているでしょう。
やはり学生は、他力本願なのでしょうか。