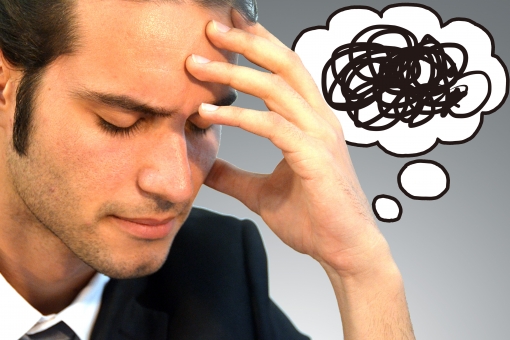中小企業のインターン活用
ここ最近の就職(採用)市場は、企業の採用枠の拡大をうけて学生に有利な市場に変化しています。
リーマンショック以降の就職難の時代からみると雲泥の差といってもいいほど中小企業の採用はやりづらくなってきています。大企業でもなかなか思うように採用が進まないケースも増え、それを少しでも解消するためにインターンを取り入れる企業が増えたり、あるいはインターンの受け入れ方法を学生が参加しやすいように変更したりする企業も増えているようです。
そんなインターン市場を受けて中小企業のインターン活用に関して考えていきたいと思います。
■採用が思うに任せない中小企業

学生の売り手市場になればなるほど欲しい人材の確保が難しくなるのが世の常です。2016年度(2017年卒業の学生)の採用活動をみると大手企業でもこのような体感(採用しにくいという感想)をもっているので、いわんや中小企業であれば言うに及ばずというところでしょう。長期的にみても若年労働力の減少は確実なので、今後はどのような工夫を行って新卒学生を採用していくのか各社とも知恵を絞る必要があります。
そのひとつとして注目されているのがインターンシップです。インターンシップは、学生の身分のまま職業体験ができるので、学生側からみるとインターンに参加することで、その際経験した仕事や先輩社会人との会話を通じて知識を増やすことができ、それを基に就職活動の大きな指標とすることができます。企業側からみると就職(採用)活動前に学生と接触できることと、インターン参加学生の中からいい学生の品定めができる点が大きなメリットとなります。
それではインターンシップ実施とは企業学生双方にとっていいことづくしなのでしょうか。このあたりのことを考えていきたいと思います。
■労力の消費はある程度覚悟して
企業側からみると、インターン制度は全てプラスに働いてくれるといいのですが、一概にプラス面ばかりではありません。インターンでいい学生と知り合ってそのまま自社に就職を決めてもらえればいいのですが、一概にそう事は都合よく運ばないことが殆どだからです。
よくよく考えると新入社員の育成指導ひとつ例に挙げても既存社員には相当な労力がかかります。そんな労をかけながら新卒で入社した人が会社戦力になってくれるまで、どうでしょう、早くて1年、業種や職種によっては3年ほどかかるのではないでしょうか。
社員と決まっている人に対してであれば、将来の戦力として考え、多大な労力をかける価値もありますが、今後、入社してくれるかどうかわからないフリーな状況の学生に対し社員同様の接し方で職業経験させることにはそれ相応の労力と負担が現場にかかるので、インターン導入においてはそのあたりのプラス効果とマイナス要素を検討する必要があります。
■職業体験としてのインターン
確かに学生側からみるとインターン制度はプラス面が多いようです。マイナス面だけで考えると、一定期間社会人としての環境に身を置くので、学業の時間が割かれ学生としての生活に影響を与えるということくらいでしょうか。プラス面では、やはり普段とはまったくかけ離れた、会社と言う環境下に身を置くことができ仕事を体験できるという感覚を身を持って感じられることが大きいと思います。
アルバイトでは飲食店のホールサービスやキッチンなどの仕事。あるいは学習塾の講師。こんな仕事は学生時代でも触れる機会が多くありますが、たとえば、営業職のような仕事は学生身分のままアルバイト環境で体験する機会は殆どないでしょう。自分が目指そうとする業界のまさに現場の仕事に触れ体験できることはこれから社会を目指す学生にとってはまたとない経験値となります。
インターン制度は、企業として、自社への就職勧誘という究極の目的が確かにありますが、そこを全面に出し過ぎてしまうとインターン本来の目的から逸脱してしまいます。インターン本来の目的である、学生に社会経験をしてもらい先々の職業選択の指標にしてもらうという社会貢献。この基本的考え方でインターンを受け入れ、その上で、企業側・学生側のベクトルがうまく合致すれば自社入社へ向け勧誘を行ってみる。インターンにはこんな考え方を持って臨むと良さそうです。